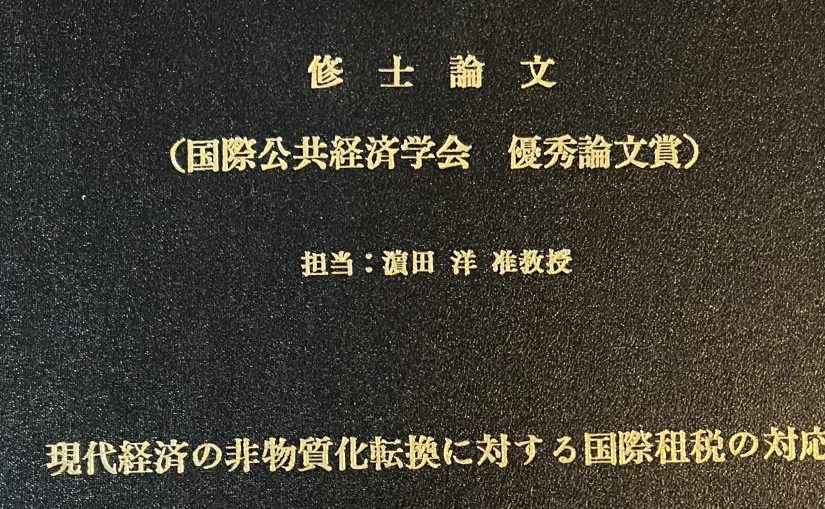この2月の初め、現在在籍中の大学院の前期博士課程(いわゆる修士課程)の総まとめとも言うべき修士論文が完成し、無事、担当指導教官と教授会の承認を頂きました。
長期履修制度を利用し、コロナ禍の真っ只中の2020年から、ほぼ4年をかけての大学院生活の集大成とも言うべき修士論文は、本文61ページ、添付資料196ページとの計257ページ(約35万字)のボリュームになり、このブログに掲載しても、全文を読み通して頂ける根気のある方はおられないだろうと思います。
ただ、たまたま、ある学会誌に、この論文の要旨をまとめて投稿する事になり、A4 約9枚の量になりましたので、以下に掲載してみます。ご興味を持って頂ける方がおられましたら、どうぞご一読下さい。
********************************
現代経済の非物質化転換に対する国際租税の対応
ー 欧州裁判の二つの一審判決の問題点からの考察 ー
兵庫県立大学経済学部大学院 松賀正考
1. はじめに
現代の国際経済社会は、新しく生まれたいくつかの要因から来る激しい潮流変化の中にある。近年の国際経済は、デジタル化とネットワーク化という要因によるデジタル経済の急速な発展とそれに伴う経済のグローバル化によって大きな変化を遂げ従来の思考の枠組みでは対処できない質的転換が進んでいる。このような要因の変化によって様々な大きな現実的経済現象が引き起こされている。
このような状況に対して、国際的な課税の枠組みは1648年のウェストファリア条約による国民主権国家が成立した後、その課税原則の枠組みの中での対応から抜け切れていない。すなわち、国民国家の内部に限定された課税権力しか行使できないという制度的建前である。そして、その激しく変化する国際経済の現状と、一方での従来からの国内的課税体制の中での対応策との間の根本的矛盾が問題の解決を難しくしている状況が生まれている。その重大な問題の一つに「巨大多国籍企業による極めて巨額な租税回避問題」がある。
GAFAと総称される企業の中でも、時価総額で世界一を競うまでになったアップル社の国際的な租税回避も、その明からさまで大胆なスキームは極めて目立つもので、このような問題は国際的租税回避として注目され始めた2010年代から様々な形で取り上げられ論議の対象となって来た。
一昨年判決が出されたEU一般裁判所のアップル・アイルランドとEU委員会との紛争ではそのような矛盾から生ずる様々な問題点が象徴的に現れていると思われる。本稿ではこのEUアップル裁判の一審判決を通して、このような現代的課題について検討、考察したい。
2.デジタル化とネットワーク化の進展
現代の国際経済の大きな質的転換は1980年代初頭に生まれたパーソナル・コンピュータの急速な技術革新とその広範な普及拡大から始まったと思われる。それ以前の大学等の研究機関や大企業等の利用に限られていた巨大なメインフレーム=システムに対し、1980年代に入り小規模企業や個人のレベルでも、そのコンピュータ・パワーを手に入れ活用できるMS-DOS機や革新的なアップル社のマッキントッシュ等のパーソナル・コンピュータが誕生し社会の末端レベルにまでコンピュータ・パワーを利用できる技術環境が進展し始めた。
さらに、1990年代に入りPCのそれぞれが単独で利用されるスタンドアローンでの形式から、PC同士が連携し合いデータの共有や共同作業がなされるネットワーキング技術が進化発展し始め、さらにより重大で画期的な技術としてインターネットによるグローバルなレベルでのネットワークの進化発展が進んだ。このインターネットに関わる技術の急速な発展によって、PCは世界的ネットワークの端末として世界のあらゆるコンピュータ同士が繋がり連携する情報環境が誕生することになり、PC等のあらゆる情報端末の連携によるグローバルで巨大な情報システムが発展していくことになった。
そして、このような画期的で巨大な技術革新とその発展は経済分野の様々な領域で従来の状況とは決定的に異なるパラダイムの大きな変化を引き起こして来た。それは例えば15世紀のグーテンベルグによる印刷技術の発明が、それまで教会に独占されていた聖書を印刷本によって誰もが所持できるような状況を生み、この変化がマルチン・ルターによる宗教改革につながったとされる歴史に比するかもしれない。あるいは、イギリスで発明された蒸気機関によるエネルギー革命が大英帝国としてのイギリスのグローバルな支配につながったとされる第二次産業革命の大きな技術革新と比べる方が適当かもしれない。その意味で、これを第三次産業革命として見るべきではないかと言う見解もある。そして、この産業革命を先駆的にリードした米国企業は、GAFA等のハイテク企業を中心に国際経済世界の支配的地位を占めるに至ったと考えるべきであろう。
3. 経済の非物質化的変化と国際経済の急速なグローバル化
このデジタル化とネットワーク化が大きな社会的影響を持ち始めた1995年、この新しい技術が及ぼす広範な社会的影響について、ニコラス・ネグロポンテは、この革命的社会変化の本質をついた著書として全米ベストセラーになった著書『ビーイング・デジタル』の中で、現在起こりつつある変化は、物質の最小単位である『アトム(原子)』から情報の最小単位である『ビット』への変化であるとその本質を比喩的に表現している。
そしてこのようなデジタル化とネットワーク化による状況変化が経済世界にもたらす質的変化は極めて多面的なものである。それは経済活動における価値の比重が従来のような土地・工場・機械設備等の有形資産によって物的な商品を製造し、これを消費者まで搬送し販売する形態よりもデジタル情報を収集・集積・加工し、このような形の情報そのものの価値へと移ることになる。また、そのような情報を中心とした経済活動に伴って集積される顧客情報などのビッグデータやビジネス活動のために構築された情報システム、技術的ノウハウ、さらにデザインやブランド等のいわゆる無形資産のウェイトがますます増大して来ている。このような経済状況の大きな変化を、諸富徹氏は「経済の無形資産化」「非物質的転回」という概念で「資本主義の新しい形」として見直すことを提言している。それは確かに現代経済の質的変化の核心をついた分析であり、このような概念を通して初めて明らかにされる経済現象が存在すると思われる。
デジタル化、ネットワーク化による現代経済の潮流変化はさらに国際経済の急速なグローバル化という現象も引き起こした。すなわち、小型PCの広範な普及による様々な分野でのデジタル化とインターネットの発達による世界的なネットワークの形成によって、経済活動に伴う情報は、デジタルデータ化されて国境を軽々と超え、瞬時にグローバルな世界で移動することが可能になった。この状況変化は経済の無形資産化と併せて従来の経済的枠組みと大きな矛盾・衝突を生むことになった。
現代経済の主役に躍り出た主として米国のIT巨大企業において、そもそもそのビジネスは基本的にインターネット上のデジタル情報に関する有形・無形の商品やシステムを開発・普及・販売するものである。したがって、そのビジネスの中心は従来我が国が得意としたような、いわゆるモノ作りとは異なり、Mac PCやiPhone を販売しているアップル社でさえ自社の工場を持たないファブレス企業である。そのビジネス活動の中心はデジタル情報をネットワーク上で使うための製品の企画、デザイン、ブランド等に特化している。したがって、その企業資産も、生み出される製品価値も、形を持った有形資産よりも、モノとしての形の無いシステム、デザイン、ブランドである。そして、このような企業においては、その生産する商品もそれを生み出す企業の資産も、そのビジネスにおいて生み出される企業利益も無形資産が中心である。
このような企業が多国籍企業として国境を跨いでグローバルな国際ビジネスを展開する場合、その企業の資産や生み出される利益もインターネット等の高度に発達した情報通信手段を通して瞬時に国境を越して移転することが可能になる。そのため、その資産や利益を外部から把握する事は極めて困難になる。また、その企業活動において生産のための企業資産の移転や帰属、利益の発生した場所やその帰属等の計算・測定や把握も同様に困難になる。すなわち、国際的多国籍企業において国籍の異なる子会社の間で、ライセンスやブランドという形の無い資産をやり取りすることによって、利益や経費を海外子会社との間で移転し利益の帰属を付け替えることが簡単に行えることになる。さらにまた、最近パナマ文書等で暴露され社会の注目を浴びる事になったように世界各地に存在するタックスヘイブンへの資産の逃避もごく容易に行える状況が進んだ。その結果、場合によっては国家予算規模にも上る巨額の資金が経済のグローバル化によって国境を越えて、各国からの何の規制も受けず、闇の金庫に流れ込み蓄積される事態が生まれている。すなわち経済のデジタル化、ネットワーク化によって加速されたグローバル化は国際経済活動を活性化するだけではなく、国際経済において大きな闇を作り出している側面もある。
後述するように、このような形で、本来なら、これらの企業が活動し、恩恵を受けている各国の財政収入に入り、各国における福祉政策を始めとする様々な政策に使われるべき巨額の資金が複雑で巧妙なスキームによって各国の管理外のルートで堂々とタックスヘイブンの闇の金庫の中に消えているのである。このような形で我が国の国家財政に入るべき財政収入の額は、ある推計調査によれば2013年において468億ドルに上るという。日本円換算ではおよそ6兆円余りであり、2020年度の法人税収12.1兆円の半分に近い。このような形でタックスヘイブンなどの暗闇の中に消えていくのでなければ、広く国民の負担になる消費税の増税など不要になる規模なのである。ロシアのウクライナ侵攻を受けて急変する国際情勢の中、防衛費の大幅な増大から、増税議論が高まる中、国際課税の問題は決して一国民に無縁な遠い世界の出来事ではなく、我々個人の足下に直結している問題なのである。このような事態に対して、手をこまねいて放置されるべきではないであろう。
4. EUアップル裁判の背景とその判決内容
前述のようにアップル社の国際的な租税回避体制が大きな注目を浴びたのは、2013年米国上院で開催された公聴会からであろう。これは、一連の米国巨大国際企業のオフショアへの利益移転問題の第2部として、2013年5月に開催されたもので、同社の複雑で巧妙かつ大規模な租税回避のスキームが白日の元に晒され、厳しい批判の議論が行われた。
さらに、2020年7月15日、EUの第一審を担当するEU一般裁判所で、EU委員会が同社とアイルランドに命じた裁定を巡る裁判の判決があった。その紛争をめぐる金額が1兆5000億円相当にものぼるという事もあり、国際ビジネス分野のマスコミも注目していた裁判であったが、その判決がアップル側の勝訴となり、EU委員会が敗訴した事から、今後の国際経済への影響も考える時、様々な反響と関心を呼んだ。この裁判の経緯と判決内容に興味を持ち、その判決の意外さに疑問を感じ、この裁判を巡る背景と内容を理解するため、判決文そのものの内容を検討した。
1)本裁判の背景と経緯
まず、この裁判の原告はアイルランドおよびアップルグループの2社の子会社(ASI、AOE)であり、訴えられた被告はEUの行政機関であるEU委員会である。このような構図になったのは、これに先立ち2016年EU委員会がアイルランドおよびアップルの子会社2社に命じた裁定がある。この裁定の中で、EU委員会は、アイルランドがアップルの子会社との間で合意してきた税務事前協定(タックスルーリング TR)は、EU法に反する国家補助(State Aid)にあたるとし、このTRを取り消し、このTRによりアップルの子会社に与えられた差別的優遇措置の回復を命じた。
この裁定によって命ぜられた追徴額が1兆5000億円相当という巨額に上ったのである。
EUが設立されたそもそもの主要目的の一つが、公平で開かれた単一の自由競争市場を作り出すことでもあり、過去にもEU委員会が加盟国の『国家補助』を否認して法人税の追徴を命じた例はいくつかあったが、このEUアップル裁判での追徴額は約1兆5000億円と桁違いのレベルであり、これほどの巨額の例は無かった。
この巨額な追徴を命じたEU委員会の裁定の無効を求めて、アイルランドおよびアップル子会社が起こしたのが今回の裁判である。
アイルランドの財政規模を歳入で見れば、2015年で706億ユーロ、日本円では8.9兆円である。つまり、今回の裁判の結果としての追徴額はアイルランドの年間の歳入額のほぼ1/6にも上る巨額である。しかも、この裁判でEU委員会の主張が通れば、この巨大な追徴額がアイルランドに入るにもかかわらず、アイルランド(とアップル)はその追徴を拒んでいることになる。それは、ある意味で奇妙な構図であるが、それだけ、アイルランドの経済発展にとって外資の導入とIT産業等の高付加価値産業への構造転換が目先の歳入増加よりも重要な課題である、という事を意味するのであろう。
2)判決文の構成とその概略
さて、本裁判の70ページを越す判決文のうち、まず、I.係争の背景の詳細を見ていくと、最初にアップルグループの歴史について簡単に記され、次にASIとAOEというこの裁判の原告である二つのアップル子会社の説明がある。この部分の説明は、単なる事実の説明に過ぎないが、この裁判の核心的な意味を持っている部分がある。その記載の重要点の第一は、この裁判の原告である二つのアップルの子会社は、単なるヨーロッパの片隅のアイルランドで細々したビジネスをしているだけの会社ではなくアップルグループの世界戦略の内、南北アメリカ以外の全ての地域を業務対象範囲としている。
高久隆太氏によれば、例えば2011年のアップル全世界順売上高の内、ASIの純売上高は実にその44%を占めており、アップルグループ内において堂々たる中核的存在の一つなのである。さらに税引前利益で見ると、アップル本社を上回る利益を上げている・・というより、アップルグループの国際的税務戦略の中で<本社以上の利益が割り当てられている>会社と言うべきかもしれない。
もう一つの重要点は「ASIとAOEは共にアイルランドで設立された会社であるが、アイルランドにおいて納税義務を持つ居住者ではない」(Par 3)という点である。これは、アイルランドの国内法である統合税法97第25節(1)の「我が国における非居住者である企業は、我が国における支店もしくは代理人を通して商取引を行なっていない限り、法人税を課されることはない・・・」とつながって大きな意味を持つ。つまり、ヨーロッパの片隅のアイルランドに設立されたアップルグループの小さな関連会社であるASI(およびAOE)はグループの世界的租税戦略の中で巨大な利益を割り当てられているが、アイルランドに居住していない外国法人として、アイルランドへの納税義務はなく、しかもこの事は、アイルランドの基本的租税法の統合税法97に置かれた条文で規定されているのである。
さらにもう一つの重要なポイントは、このASIおよびAOEはアイルランドにおいて本社の社屋等の物理的拠点も本社業務のために雇用された従業員も一切無いのであるが、不思議な事にアイルランド支店は社屋も従業員も存在する、という事である。すなわち、アップルグループの中で、巨大な売上げと利益を上げている、あるいは、利益を割り当てられているASIとAOEの本社的存在は一切存在せず、一方で、そのアイルランド支店だけは存在している、という奇妙な状況がある。
実は、この支店の存在と位置づけ、こそがこの裁判の最大のキーポイントと言える。
その事はこの全文72ページに及ぶ判決文での語句検索を行った時に現れる「branch(支店)」という語の出現頻度の異常な多さからもうかがえる。「branch」の語は、全パラグラフにわたって満遍なく出ており、その頻度は実に412回に上る。全パラグラフ数が509であるから、ほぼ殆どのパラグラフに登場すると言ってもよいような頻度である。
そして結局、この裁判で争われた争点が何であったのかを一言で言えば、それは<アップルグループの中で巨大な売上げと利益が割り当てられているASIとAOEの課税利益は、その物理的存在の無いこの2社の本社に帰属すると言えるのか、あるいはまた本社の存在が認定できない以上、物理的存在が認められるアイルランド支店に帰属させるべきなのか>という事に尽きる。
委員会の立場は、ASIとAOEの巨大な利益は、実体が存在するそのアイルランド支店に帰属する、というものである。
この委員会裁定はアイルランドがASI、AOEとのタックスルーリング(事前税務協定)によって、この2社に対して差別的優遇措置を与えていると認定し、これを取り消し、アイルランドはこのアップルグループの2社から本来の公平な課税ルールに沿った額を追徴するべしという内容であった。その裁定で命ぜられた1兆5000億円相当という追徴額の巨大さによって一気に世間の耳目を集めたのであるが、この裁定の中で、委員会が指摘した問題は、ASI、AOE に帰属されるとしている大きな課税利益は、その2社が外国法人であるという理由からアイルランドの課税権が及ばないとしているが、その本社の物理的存在が全く認められない以上、この利益は現に物理的に存在している両社のアイルランド支店に帰属させるべきものである、と主張したのである。
そしてこの判決文全72ページ中、43ページ(p.15~67)を占めるIII. Law(審理)の部分では、議論は委員会がその主張の論拠として示している3つの論点を巡って展開されている。しかし、それは基本的に「ASIとAOEに保有されているアップルグループのIPライセンスからの利益のアイルランド支店への帰属」問題なのである。
その議論の展開を追い、その論争の経緯を要約すれば、こんな形になるだろうか・・・
まず、EU委員会は、「公平に開かれた自由な競争市場の形成」という錦の御旗を掲げてEU機能条約107(1)項の<加盟国によって又は加盟国の施設等を用いてその他のいかなる形態による ものであるかを問わずおこなわれる支援であって、特定の事業者又は特定 の商品若しくは役務の生産を優遇することにより競争を歪曲し又は歪曲の おそれをもたらすものは、加盟国間の取引に影響を与える場合には、域内 市場の理念に合致しない>という「107(1) TFEU」( III-D 31回を中心に43回出現)を前面に押し出し、「国家補助( State Aid )の禁止」という大命題(主に III-C に9、Iに6、等 計26回出現)を中心に、「独立企業の原則(arm’s length 主にIII-D 37、III-E 23 を中心に82回出現)」や「OECD承認アプローチ(Authorized OECD Approach 42回出現)」、「OECD移転価格ガイドライン(OECD Transfer Pricing Guidelines 21回出現)等の原則を持ち出して、アイルランドとASI、AOEを攻撃しようとした。つまりEU委員会の主張は、主として、あるべきEUの政治的観点からの理論的攻撃であった。
一方アイルランド・アップル連合は政治性の強い理論戦の仕掛けには一切乗らず地味な法律論に徹しアイルランドの国内法である統合税法97(TCA 97)の「我が国における非居住者である企業は、我が国における支店もしくは代理人を通して商取引を行なっていない限り法人税を課されることはない」という条文に閉じ籠り、「もし支店や代理店を通しての取引をしている場合は法人税法において定められている条件の例外以外では、それがどこで発生していても、その課税収益に対しては法人税が課される」という条項を逆手に取って、<ASI、AOEの現地支店は単なる出張陣地であり、そこに財物は無い>という主張を繰り返すだけであった。
この第一審の戦いでは、EU委員会の3つの全ての論拠は、この判決において否認され、アイルランド側の泥臭い法律論作戦が功を奏した形であるが、結局決め手になったのは、以下のような『委員会の立証責任』を要求する裁判所の判定であった。このような『委員会の立証責任』を求める趣旨の文は、本判決文中、繰り返し現れている。
例えば、Dのパート中では、
243 その主要な論拠において、委員会は、要するに、アップルグループのIPに関わるASIとAOEの利益(それは委員会の議論によれば二つの会社の全利益の中の相当な部分に当たるのであるが)は、そのIPの管理をしうる従業員をその支店の他に持っていなかったのであるから、アイルランド支店に帰属させなければならない、と考えたが、しかしながら、そのアイルランド支店がそれらの管理機能を果たしていたという事は実証していないのである。
同様の指摘はD、Eのパートで繰り返しなされている。
3)この判決文についての一般的評価と私見
このような言わば空中戦と地上戦という構図での論争を続ける限り、この裁判の決着の方向性は変わらないであろう。実際このEU一般裁判所での第一審の敗訴を受けて、EU委員会は、上級裁判所であるEU司法裁判所に控訴し、その控訴にあたっての控訴理由が発表されている。
しかし、その主張はEU全体の立場からの一種の政治的主張が中心となっており、EU一般裁判所の判決で認められたアイルランド・アップルの主張とは全く噛み合っておらず、
「我々は抜け道に対して適正な法的規制をし、透明性を高めるための努力を続ける必要がある。」
と言いながら、具体的にどのような法的論理によって原告側の主張を崩すのかについては、ほとんど無策に見え、このようなEUの政治的立場からのみの理論戦では、原告の主張の議論を崩すことは出来ないと思われる。
普通の社会人的常識感覚では、むしろEU委員会の主張は現在のEUの経済的状況から考えて妥当なものではないかと思われる。ただ、ASIやAOEの本社的実態が無いから『排除の論理』によって自動的にASIとAOEの売上げと課税利益はそのアイルランド支店に帰属するとみなすべきだという論理はやや乱暴で飛躍があり、その論理的粗雑さに付け込まれた事が、この裁判の敗北を招いた原因ではないかと思われる。
また、この裁判に対して、EU関連の租税専門家を中心としたタスク=フォースの意見書や国際租税法の専門家の判決評論も出されているが、これら租税法専門家の見解としては、EU委員会の主張は、やはり租税回避に対する批判、EUのそもそもの設立意義にも関わる『国家援助(State Aid)』を元にした批難に偏り過ぎており、厳密な租税法の解釈から見る時、その主張には無理があり、残念ながら今回の一般裁判所の判決を妥当なものと見ざるを得ないであろう、との見解が多いようである。
しかしながら、今回の問題を素朴な感覚で見直すと、アイルランドで設立されたと言いながら、本社としての物理的実体も全く存在せず、雇用されている従業員も居ない、まさにペーパーカンパニーそのもののASIとAOEにアップルグループの無形資産(IPライセンス)の大きな部分が帰属されるという事、さらにそこから生まれる巨大な利益に対してはアイルランドに居住していない外国法人として課税を逃れるという手法の不自然さが際立って感じられる。このようなスキームは明らかに意図的作為的なものであり、巧妙で大規模な租税回避とも見える。したがって、法人の課税的居住性(tax residency)の問題、そして、実体が全く無いペーパーカンパニーに、これまた実体の無い(intangible)無形資産(IP licenses )を恣意的に割り当てるという手法が社会的に許されるのか、という視点から問題を整理、追求するべきではないだろうか、というのが、私の素朴な感想である。
法人の課税的居住性や無国籍性(stateless)という事に関しては、III.審理のA.のパートにこれに触れた記述が何箇所かある。しかしながら、この問題に関しては、論争は発展せず、議論は全く行われていない。むしろ、問題として議論すべきはこのテーマであって、ここで委員会は重大な隠れた論点を見逃してしまったのではないか、との思いもする。
矢内氏の同じ論文によれば「AOIは、2009年から2013年の間に、300億ドルの所得がありながら、非居住法人として申告もせず、5年間いずれの国にも納税していない」と言う。そんな理不尽で無法な状況が放置されているとは驚く他はない。ただこの問題は逆に個々の国家レベルや国家の集合体としてのEUを飛び越え世界市民的立場から考えるべき対象であって、あくまでEU内の法制の中で考え行動するしかないEU委員会の思考の埒外だったのかもしれない。しかし、いずれにしても、これらの多国籍企業グループの課税問題についての基本的理論やそれに対応する政策論が余りにも追いついていないのではないか、と感じられる。
一方、IP licenseについては、全文中に44回現れており、IPのみでは296回も出現している。
いずれにしても、この無形資産としてのIP licensess の問題が重要なポイントの一つであることは確かである。すなわち、この裁判を難しくしている背景には、現代経済の様々な面での非物質化への動きが深く関わっている。このような経済の質的変化を踏まえた総合的な視野からの国際的枠組みの中における取組みが必要であり、そのような政策的取組みがなさなければ、この裁判が示す大きな本質的問題を根本的に解決する事は不可能であると思われる。
5. 国際課税をめぐる各国および国際的対応
以上述べて来たような時代の潮流の変化と構造的矛盾に対して、各国や国際組織は様々な形でその矛盾の解消のための取り組みを進めて来た。前述のように、問題となる巨大IT多国籍企業を多く抱える米国においても2013年の議会公聴会をはじめとして問題となる企業を対象に厳しい追求が行われ、その対応策が模索されて来た。
また、これらの米国発の巨大多国籍企業に席巻されて来たヨーロッパ諸国でもEU委員会を中心に様々な対策が進められて来た。EUはある意味で従来の国民主権国家の枠組みを超えた連合組織であるため、租税問題における各国の協調を重視している。この面から各国において特定企業に特別な優遇措置を与えることを単一経済市場としてのEU域内での公正な競争条件を歪める『国家補助(State Aid)』とみなして、これを認めない姿勢である。このようなEU域内の加盟国による特定企業への『国家補助』は、しばしばEU委員会からの指摘と裁定を受け、場合によっては当該国との司法的争いがEUの司法機関で争われてきた事例が数多く存在する。
さらにまた、主要な経済先進国の国際組織としてのOECDやG20等でも、近年の国際経済環境の枠組みの急激な変化によって生じている矛盾や問題に対応するための様々な取り組みが続けられている。いわゆるBEPS(Base Erosion Profit Shifting 税源侵食と利益移転)に対してOECDを中心に粘り強い協議と合意形成がなされてきたが、2021年7月世界全体のGDPの90%超を占める130の国・地域が、新たな国際課税ルールに合意、参加した。多国籍企業がどこで事業を行うかに関わらず税を公平に負担することを確保するための2本の柱からなる新計画に参加したのである。世紀的抜本改革として歓迎されたこの二本柱の合意の一つ目は、各国における法人税率を最低15%とするものであり、経済のグローバル化によって自由に動き回る多国籍企業への課税に関する『有害な租税競争(Harmful Tax Competition)』から来る過度な低税率競争に歯止めをかけようとするものである。さらに二つ目の柱は、経済の非物質化によって企業利益の適切な把握が困難な状況からの税源の逃避に対する対策としての導入が決まった『デジタル課税』の導入である。
このような国際的対応が進む中で、では我が国として国際課税問題について、どのように考え、どのような対応をするべきかについても検討する必要があると思われる。
なお前述のように、2審制のEUで、今回検討対象とした第一審の一般裁判所の判決に対して、EU委員会は上級審のEU司法裁判所に上告しており、この問題の最終決着はEU司法裁判所の最終判決を待たなければならない。第一審の判決後既に2年半が経過しており、遠からずその最終判決が出るものと思われる。関係専門家の予想として、政策的あるいは道義的観点からはともかく、租税法の論理的視点からは、判決が覆る可能性は薄いという意見が多いようであるが、最終審の結論が注目されるところである。
<本文 11,634字>
《Summary》
The current international economy is undergoing major qualitative changes due to the digitalization and networking and globalization of the economy. On the other hand, the international taxation regime remains based on the domestic taxation regime under the nation-state system established by the Treaty of Westphalia in the 1600s, and the systemic contradiction between the two is causing major problems in various forms. The EU Apple case, which was decided by the first instance in July 2020, seems to symbolize such contradictions in the current international economy. Through analysis and examination of the content of this judgment, I have considered the contradictions and problems in the modern international economy.
<注>